建新ブログ BLOG
2025.08.19
- カテゴリー 新卒ブログ
“理の芽吹き”
お久しぶりです!新卒の坂本です。
7月1日をもって積算購買部へ配属となりました。まだまだ若く未熟の身ではありますが、改めて身が引き締まる思いです。誠心誠意、全身全霊をもって、がんばります!
前回のブログには、ありがたいことにたくさんの反響をいただきました。その中でも特に「数学の話を聞いてみたい」というご要望が多かったので、今回は数学について、少し掘り下げてお話ししたいと思います。
私は大学で、理学部数学科というところで数学全般を学んでいました。「理系」の「理」とは、物事の基本的なルールや法則を意味します。つまり、理系の人々とは、この世に存在するあらゆる「理(ことわり)」に対し、実験や研究を通じてアプローチを試み、まだ解明されていないものを明らかにし、完全な理解を目指す人々のことだと私は考えています。
数学は、人類が狩猟採集生活から農業へ移行し、保存や貯蓄、そして財産という概念が生まれたことで、その必要性から誕生しました。取引や交換にともなう計算が、数学の始まりであり、「理」の芽生えだったのです。この計算をより深く、抽象的に研究するのが代数学という学問です。代数学では、高校数学で習うような数の代わりに文字を用いるだけでなく、足し算や掛け算といった演算そのものの定義を改めて考え直すという、非常に奥深い研究を行います。
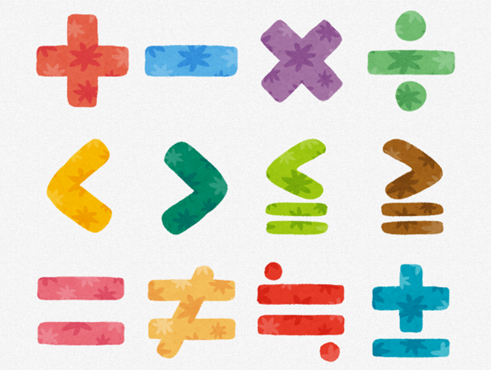
ここで「3 + 1 = 4」という計算を考えてみましょう。これは私たちにとってあまりにも当たり前なことですが、実はそこにはさまざまな定義が隠されています。たとえば、「+」は数字を足し合わせる演算であること、「=」は左辺と右辺の値が等しいことを示す記号であること、そして特別な記述がなければ10進法で計算することなどです。これらの定義を一つひとつ確認することで、初めて「3 + 1 = 4」という結果が導かれるのです。もしこれらの定義が異なれば、「3 + 1」が必ずしも「4」になるとは限りません。
この考え方は、私たちの仕事にも通じる重要なポイントです。建築の現場では、設計図がミリメートル表記であるのに対し、大工さんや職人さんが尺貫法という日本古来の寸法を用いて作業することがあります。この定義のズレを無視してしまうと、設計段階と現場に大きな乖離が生まれ、最終的に建築基準法を満たせなくなってしまう可能性もあります。
一見、華やかさとは縁遠い代数学ですが、物事の基本的な定義を再確認し、正確な計算を行うことの重要性を教えてくれます。これは、私たちが日々の業務で設計図や仕様を確認し、正確に積算・発注する姿勢と全く同じことです。
次回は、より実用的な数学の話と、建築分野との関わりについてお話ししたいと思います。ご期待ください。
————————————————————————————————
新卒ブログでは、魅力あふれる横須賀の街や建新について、
これからもたくさん発信していきますので楽しみにしてください。
また、建新ではブログの他に各SNSにて神奈川県の魅力や建新のお家について発信しております。フォローやチャンネル登録の程、よろしくお願いいたします!
【YouTube】
【TikTok】
【Instagram】
【Twitter】
【Facebook】
————————————————————————————————






